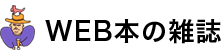第三回 女の時代、メディアの時代(中編) 対談ゲスト:酒井順子さん(エッセイスト)
【対談ゲスト:酒井順子さん(エッセイスト)】
1978年というエポックメーキングーー『MORE』『ミスヒーロー』
酒 70年代後半って『主婦の友』とかの四大主婦雑誌の売り上げがどんどん減っていった時期らしいんです。あともう一つ雑誌的に1978年が大事かもしれなくて。『JJ』の月刊化、『ギャルズライフ』創刊、あと『プチセブン』創刊。
平 わたしが作った年表によると、78年『ギャルズライフ』創刊、『Fine』も創刊。
酒 え、それ大事ですね。『ギャルズライフ』はギャルの源流。あと「キャリアウーマン」「いい女」「翔んでる女」ブームもこの辺じゃないですか。
平 78年の西武百貨店のキャッチコピーが「女の時代」です。そして『JUNE』も創刊してます。「腐女子」の源流......。
酒 オタク、サーファー、ギャルがみんなこの年に出てますよ。
平 すごい!
酒 80年代的文化の萌芽っていうのがこの辺から始まったっていう。
平 ちなみに前年の77年は『クロワッサン』も出てるんですけど、実はリブ雑誌、フェミニズム雑誌がめっちゃ出てるんですよ。
酒 『MORE』(集英社)とか?
平 そう、『MORE』(注1)もだし、あとあんまり知られてないんですけどJICC出版から出ていた『わたしは女 : magazine for new women』(注2)。
酒 (表紙の絵を見て)破いている。エプロン破いてる。
平 (笑)。あと牧神社っていうところから出ていた雑誌『フェミニスト JAPAN』(注3)......。
酒 表紙はヨーコ・オノですか、それ?
平 そう。「新しい青鞜」と書いてあるんですが、当時上野千鶴子さんは非常に苦々しく思われたらしくて。この雑誌を編集されてた青学の先生だった渥美育子さんという方が、アメリカに行って第2波フェミニズムの波を受けて、日本にも!と思って創刊したらしいんですけど、リブの人たちからすると、前から日本でやってたのに今更そんな......だし、リブ運動を無視して青鞜まで先祖返りしているというので苦々しく思ったっていうのを書かれてました。この雑誌は2年ぐらいで終わっています。ちなみに、73年には『女・エロス』(社会評論社)(注4)っていう雑誌も出てまして(笑)。
酒 いろんな雑誌が出てたんですね、リブ関係の。
平 そうなんです。『パンドラの匣』(牧神社)(注5)、これも77年創刊なんですよね。ぱっと見全然フェミ系雑誌に見えないんですけど。例えば対談には若い矢野顕子が......。
酒 えー!
平 煙草を吸う矢野顕子が長谷川一夫と対談してる。
酒 あら、きれい。
平 吉田ルイ子(注6)が写真を載せてたり......鴨居羊子(注7)が寄稿していたり。『パンドラの匣』はわからないけど、『女・エロス』は全員女性です。あまりにも先鋭化しすぎてすぐなくなってしまった(笑)。こういう雑誌が77年に出てました。
酒 そういう真面目なフェミの人たちの勢いと、80年代の俗な文化の勢いとの、潮目が変わる頃だったのかもしれないですね。
平 そうですね。リブも80年ぐらいに入ってから運動としては下火になって、みんなそれぞれのイシューにいったっていう話もありますしね。そして80年にまた女性誌創刊のブームがあって『25ans』(ハースト婦人画報社)、『コスモポリタン日本版』(集英社)、そして誰も覚えてない『ミスヒーロー』(講談社)。
酒 『ミスヒーロー』、たまに読んでましたよ。
平 えっ、本当ですか?
酒 先輩が載ってたりしたので、キャーキャー言いながら。
平 へえ。あと『TODAY』(文化出版局)っていう雑誌もあったけど多分短命だったと思います。
酒 『Fine』は、今のEXILEとかあの辺の文化の源流かも。
平 そうですね。最初からサーファーの雑誌でした?
酒 はい。「陸(おか)サーファー」(注9)も流行っていたので。
平 ファッションだけのサーファー?
酒 そう。この当時はサーファーディスコとかもいっぱいありました。
平 サーフミュージックをかけるディスコってことですか?
酒 そうなんです。当時流行ったバックプリントのアロハとかプカシェル(注10)とか、そういうサーファーファッションアイテムを身につけて日に焼けてる輩(笑)がいっぱいいました。
平 そこは結構くっきりわかれてる?
酒 サーファーは絶対他のディスコに行かない、とかじゃないんですけど、サーファーっぽい人が多かったのは「ナバーナ」とか「キサナドゥ」。私はノンポリだったので、サーファー系も含めいろんなカラーのところに。
平 そっか、わたし、ディスコ文化に間に合ってないんですよね。唯一行ったのが銀座の「Mカルロ」っていうところなんですが、貸切パーティーだったので普段の感じはちょっとわからなかった......。
酒 じゃあ、クラブ世代?
平 そうですね。
女子文化の進化系、ギャル文化へーー『オリーブ』『ギャルズライフ』
酒 ギャル文化の源流をわかっていただきたくて、今日は『ギャルズライフ』(注9)(主婦の友社)のコピーも持ってきました。
平 結構過激な雑誌と聞きましたが。
酒 国会で問題になるぐらい過激だったんですよ。「産んでどうするStop The 妊娠」。83年「ギャルズセックスレポート」、「女の子たちの水子供養」なんていう特集を組んでました。
平 えっ! 『ティーンズロード』(ミリオン出版)みたい。『小悪魔ageha(エイチジェイ)みもある。
酒 「赤ちゃん本当にごめんなさい」だって。
平 軽い......。すごいですね、「初体験14.9歳」! 読者だけのインタビューではあるけどすごいなあ、「Cをしましたか」だって。
酒 『ギャルズライフ』が出てから『Popteen』(富士見書房)とかそういうギャル雑誌がどんどん出てきて、あまりに過激で国会でも問題になった。多分、女性のセックスライフ体験率が一番早かったのは90年代だと思うんですけど、その頃にこういう雑誌が一番読まれていて、そこからギャルブームにつながっていきました。平山さんはルーズソックス世代ですか?
平 いえいえ。70年生まれなのでそれより前で、氷河期とバブルの間です。92年が就職の年で世間的にはバブル崩壊って言われてるけど、出版業界はまだ全然いいときでした、2000年ぐらいまでは。学生時代にバイトしてるときがバブルだった感じです。
酒 雑誌は何を読んでました?
平 私は高校生ではおもに『オリーブ』と『週刊マーガレット』(集英社)かな......。
酒 『オリーブ』も割と後期の頃?
平 今日持ってきた84年も読んでました。酒井さんが書かれてたのは何年ぐらいですか?
酒 会社員になってからも書いていたので、80年代前半から90年代前半ぐらいまでですかね。この「アボアール徳川先生」を引き継いだんです、私(笑)。アボアール徳川先生が泉麻人さんだったんですよ。
平 あ、そうなんですか! オカシ屋ケン太もですよね。
酒 そうです。いろいろな名前で書いていらして。で、あまりにも泉さんが忙しくなって、このページを引き継いでマーガレット酒井が登場しました。
平 そうなんですね。泉さんが酒井さんの最初の担当編集者って聞きました。
酒 そうなんですよ。当時泉さんは東京ニュース通信社の編集者さんで雑誌を編集していらしたので、最初高校時代に「そこに書いてみない?」って言われて。あとは『オリーブ』とか、マガジンハウスの雑誌に書いたり。私は『オリーブ』と『ギャルズライフ』を併読する高校生でした(笑)。
平 酒井さんらしいですね。
酒 俗な部分の興味は『ギャルズライフ』で満たしてましたね。初期の『オリーブ』っていろんな高校生が顔出ししていて、そういうのが楽しかった。
平 『ギャルズライフ』、噂には聞いてたけどやっぱりすごい。......でもヤンキーではないんですね、読者たちは。そんな荒れてる感じでもないですね。
酒 ヤンキーwanna beな感じですかね。
平 なるほど。唐突に「猫ちゃんの写真館」があるのも面白い。「モテモテメイク講座、日焼け少女のための」......「アメリカ少女の恋愛生活」なんて特集もあるんだ。意外と普通の雑誌っぽいところもある。そんななかで「田中康夫の女の子自由自在」(笑)。
酒 その当時の田中康夫さんって、本当すごくいろんなところで活躍してましたよね。
平 林真理子さんの「女のなりあがり講座」もある。面白そう。
酒 そう。林真理子さんのデビュー作『ルンルンを買っておうちに帰ろう』も『ギャルズライフ』も主婦の友社だから、縁があったのでは。
平 『ルンルン~』は82年発売ですか。流行を気にしなかったわたしでもさすがに読みました、発売から数年後だと思いますが。すごく面白かった。
酒 『ルンルン~』の刊行は当時の若い女性にとって、大きな出来事でしたよね。『なんとなくクリスタル』(河出書房新社)も、中学生だった私には衝撃でした。80年に発表。『25ans』と同じ年。
平 80年にあの感じは早いですね。『Popteen』(ポップティーン)も創刊年。わたしは当時は過激だから近づかないようにしようという感じだった。というか、そもそも周囲にギャルっぽい子がいなかったかも。あらためて今見ると、明治の少女雑誌創刊から80年で、少女雑誌はここまできたのか、という感じですね。
素人女性の台頭――「夕焼けニャンニャン」「オールナイトフジ」
平 昭和のメディアといえばテレビも重要ですね。最近TikTokをよく見るんですが、「夕焼けニャンニャン」の切り抜き動画がめちゃめちゃ流れてくるんですよね。当時見てなかったけどいまや結構詳しいです。「週の真ん中水曜日、真ん中もっこり夕焼けニャンニャン」。こういう言葉を女の子に言わせていたのが昭和です。
酒 「夕焼けニャンニャン」は学校から帰ると放送していたので観てました。あと、女子大生の「オールナイトフジ」。「夕焼けニャンニャン」は「オールナイトフジ女子高生スペシャル」から始まったんですよ。女子大生からのニャンニャンだったはずです。それこそ港(浩一元フジテレビ社長)さんとかがやっていたんじゃないでしょうか。
平 そう言われてますよね。あらためて見ると当時は衝撃的な番組だっただろうなって思います。出演者が素人っぽい女の子たちってこともそうなんですけど、台本があってないような感じで、とんねるずもおニャン子たちと年が近いから喧嘩になったり、ムキになって言い合いになってCM、とか。
酒 おニャン子クラブは美人ばっかりじゃなくて、秋元さんが言うところの「クラスで3番目にかわいい」みたいな子もいたし、女子大生オールナイターズもそうだったし、あの頃から完璧ではない、ちょっと抜けたところのある女の子の魅力みたいなものがアピールされていた。
平 ものの本によると、素人の女の子たちを最初にフィーチャーしたのが雑誌『JJ』で、スナップ写真をいっぱい載せたところが素人ブームの先駆けじゃないかと。
酒 そうでしょうね。読んでいて、「自分だっていけるのでは?」みたいな誤解ができるのが楽しかった。
平 当時は雑誌に載ったからってモデルとか芸能人を目指すんじゃなくて、「載った、載った」ってただ友達と盛り上がるだけなんですってね。そんな素人という鉱脈を見つけたのが『JJ』なのかも。
酒 そうですね。そこは『JJ』のお手柄ですよね。『mc Sister』(婦人画報社)も私は好きで、『オリーブ』(マガジンハウス)が出る前は『mc Sister』を読んでました。
平 『mc Sister』のほうが『オリーブ』より先なんですね。
酒 そうなんですよ、73年の創刊でした。『メンズクラブ』のシスター(妹)なので、『メンズクラブ』のMC。アイビーブームで『メンズクラブ』ができて、その後に女子版ができたので、割と早いですよね。
平 なるほど、私の高校時代の感覚では『mc Sister』は『オリーブ』の真似っこみたいな感じでした。
酒 確かに『オリーブ』が出てからシスターはもう読まなくなっちゃった。
平 『オリーブ』のほうがちょっと先鋭的なイメージですよね。
酒 雑誌専属のモデルへの憧れを最初に感じさせたのは、シスターですね。
平 なるほど。『オリーブ』にも栗尾美恵子さんとかティア&ケリとか専属モデルはいたけど、なんかこうモデル単体でどうというよりは「世界観!」って感じだった。
酒 栗尾さんは、女子高生スナップから出てきた人だったので読者に夢を与えたという......。
平 なのにモデルを卒業してCAさんになったとき、「あっ、そっちなんだ」って。
酒 裏切られたって思いました。
平 赤文字系じゃん、と(笑)。さんざん花柄を重ね着しておいてって。でも「やっぱりなあ、なんかそんな気がしてたんだよ」みたいなあきらめもありました。
酒 『オリーブ』の本を書いていたときに、『オリーブ』によく出ていた元慶應女子高の人にインタビューしたんですけれども、本当はオリーブファッションとか全然好きじゃなかった、がんばりすぎでダサいって思ってたと言っていました。そういう人は結構多い。初期の頃に出ていた成城学園の何とかさんとか、慶応女子高の何とかさんっていうあの人たちのファッションと、『オリーブ』のファッションって全然違うじゃないですか。そこにずれはありましたね。
平 逆に、公立共学の私は都内名門女子高関連の記事にあんまり入り込めなかったな。そのうちだんだんファンタジーになっていって、どこでもない国に行ってしまった。
酒 オリーブファッションは、現実ではモテないですもん。
平 真似しづらい。柄に柄を重ねたりかなり突飛ですよね。でも好きだったな。後期になってくるとオザケン(小沢健二)とかカジヒデキとか渋谷系の人たちが登場しましたね。SMAPも出てた。個人的にはそれはちょっと違うなっていう感じがありました。『オリーブ』に出てくる男の子は外国人モデルとか架空の人であってほしい。
酒 出てくる読者モデルも和光とかになってきたんですよね。学校の系統が違ってきて。そして表4(裏表紙)はいつもパーソンズの広告だった。
平 そうそう。私、知らなかったんですけど、パーソンズの創業者の岩崎隆弥さんは三菱財閥の御曹司なんですね。マツイ棒の松居一代さんが前妻。
酒 じゃあ、船越英一郎さんと結婚したのはその後なんですね。パーソンズって今でもあるみたいですよ。
平 デザインの路線はどういう?
酒 華やかな色合いとかはこの時代と同じ。誰をターゲットにしてるのかはよくわからないのですが。
平 謎の資金力があるなっていつも思ってました。かわいいけどものすごくマニアってほどのファンを見かけないのに、なぜいつも表4に広告が出てるんだろうって。大きなお世話なんですけど。アイドルとのタイアップとかもあったのかもしれないですね。おニャン子のセーラーズみたいに。セーラーズも復活してますもんね。
「族」の盛衰――竹の子族、ローラー族~くれない族
酒 話は変わりますけど、この前上野に行ったんですよ。そしたら上野公園の一部のところでローラー(注10)が男女2人で踊ってたんです。竹の子族と同時期にローラー族が原宿で踊っていたの、憶えてます? あの人達が復活してたんですよ。私と同世代の2人だったので、たぶん子育てを終えて、昔とった杵柄をもう一度という感じなのか。
平 よくTikTokの動画に出てきますよ。羨ましいなと思って見てました。ある意味では新しい中年像でもありますよね。
酒 その時、一緒にいた友達が中学時代ローラーだったから(笑)。「踊りたーい!」って言ってました。次々とこういう行動が復活してきてますね。
平 竹の子族の復活はさすがに聞かないですね、まだ。
酒 でも「ブティック竹の子」(注11)はありますもんね。今、どういう服を売ってるのかわからないけれど。
平 今は舞台衣装とかステージ衣装を手がけてるみたいですね。最近は海外から観光客もたくさん来てるし、「80年代」ブームもきてるから竹の子族のハーレムパンツとか売ったら売れそう。私もちょっと欲しい。
酒 80年代はよもや復活するとは思わなかったです。なんというか、バッドセンスな時代じゃないですか。
平 ですね。復活するって何度も言われてましたが、とうとうZ世代に刺さった。
酒 でも「族」っていなくなりましたよね。〇〇族。
平 「チーマー」が流行った90年ごろになくなったと『族の系譜学 ユース・サブカルチャーズの戦後史』(難波功士、青弓社)に書いてありました。「渋カジ族」が最後で、それらがよりワイルドになって「チーマー」になり、以降は人名やブランド名+erになっていく。アムラーとかシャネラーとか。そして渋谷系などの「系」になっていく、と。でも渋カジを渋カジ族って言ったことはなかったけど。最後の「族」はなんだったんだろう?
酒 「くれない族」(注12)っていましたね。群れている「族」ではないけど。
平 『くれない族の反乱』! 「〇〇してくれない」っていう人たちですね。
酒 暴走族はかろうじて残ってる。
平 います、います。暴走族って名乗っているのかわかんないけど。深夜に近所の中原街道をときどきぶっ飛ばしてますよ。
酒 最後の族は、トライブを自称するあの人たちなんじゃないですか。
平 EXILEか! 疑似家族みたいなのがもう流行らないのかな。
酒 テレビ番組では、「〇〇ファミリー」とかすぐ言いがちですけどね。今の若者達は、竹の子族の時代のように原宿の歩行者天国などで実際に集合しなくても、ネット上で十分につながることができる。だから、「族」を形成しなくても満足できるのでしょうね。
平 確かに。「族」が古臭いイメージなのは、大人たちが外から見て名付けてるからなのかも。
酒 距離が感じられる言葉ですよね。最近の大人って実はそんなに若者に距離を感じてないのかな。
平 若者は感じてるでしょうけど(笑)。大人は、なんなら「俺だってまだまだ若いぞ」くらいのことを思っているかもしれない。わたしも気を抜くとつい思ってしまいます。大人になる機会をすっかり逸してしまいました(笑)。
(「後編」に続く)
注1 『MORE』 1977年、働く若い女性の月刊誌として創刊。とくに80年に実施された「性」に関する本音アンケート「モア・リポート」は画期的な試みだった。以後、87年、98年にも実施されているが、2023年11月号から季刊となった。
注2 『わたしは女:magazine for new women』 JICC出版(現宝島社)が1977年7月に創刊した女性誌。特集タイトルの「結婚からの自立」、「性の意識革命」、「愛人殺し・親殺しはハッピー感覚だ!」からもわかる通り、ウーマン・リブの要素も強い。わずか1年後の78年7月号休刊。
注3 『女・エロス』 1973年11月に社会評論社から創刊された女性誌。編集も執筆も女性のみ。創刊号の「宣言」では「女たちよ!、激しい権力拒否の不断の運動として、意欲あふるる、厳しくも、楽しい自治コンミュンを創立せよ!」とオルグしている。特集タイトルは「婚姻制度をゆるがす」「家族解体にむけて」など強い言葉が並ぶ。公称部数5000部。休刊号は確認できず。
注4 『フェミニスト JAPAN』 牧神社が1977年8月に創刊した女性誌。編集部も執筆者も女性のみ。創刊号の「編集後記」には「隔月刊。年一冊は(中略)英語版を出す」とある。80年9月発行の17号で休刊。なお、編集長の渥美育子氏は現在グローバル教育研修に力を入れている模様。
注5 『パンドラの匣』 1977年4月に創刊準備号を経て6月に牧神社から創刊。女性誌ではあるが「跳び出そう!心の冒険旅行に」というキャッチフレーズや藤岡篤のサーカスのイラストからは総合誌のようにも見える。外山滋比古や長谷川一夫、橋本治など男性執筆者も登場。漫画や詩、きいちのぬりえなどもある。78年発行の「3・4号」で休刊。
注6 吉田ルイ子 1934 -2024年。日本の写真家、ジャーナリスト。大学卒業後にNHK国際局の嘱託、朝日放送のアナウンサーを経てフルブライト交換留学生として渡米。コロンビア大学でフォトジャーナリズムの修士号を取得した。ニューヨークのハーレムで撮影した写真で公共広告賞を受賞。おもな著書に『ハーレムの熱い夜』など。
注7 鴨居羊子 1925-1991年。下着デザイナー、画家、エッセイスト。新聞記者を経て、白い女性用下着や硬いコルセットしかなかった時代に明るく可愛らしいショーツやナイトウェアを作り、ファッションショーを開催するなどして革命を起こした。布地の少ないショーツを「スキャンティ」と命名。
注8 陸(おか)サーファー デジタル大辞泉によれば「ファッションとしてサーファーのような格好をしたりサーフボードをもったりしているが、実際にはサーフィンをしない人」。車のルーフにサーフボードを載せ、車内にヤシの木のミニチュアを置いて街を走っていたらしい。サーフボードはインテリアにしては高価である 。
注9 『ギャルズライフ』 1978年8月創刊。創刊号は原田治の表紙で、「西海岸ギャルズのスクールライフ」「ボーイフレンド・カタログ 有名私立高男子88名」など健全なコンテンツだったが、80年頃にはセックス関連記事が登場。競合誌として『ポップティーン』(飛鳥新社)、『エルティーン』(近代映画社)、『キッス』(学研)、『キャロットギャルズ』(平和出版)なども生まれた。84年2月の国会でこれらの雑誌が過激だとしてやり玉に挙げられて路線を変え、ファッション系の『ギャルズシティ』に改名。しかし1年あまりであえなく廃刊した。
注10 ローラー族 1980年代前半に東京原宿の代々木公園脇の歩行者天国で50年代のアメリカのロックンロールやロカビリーをラジカセで流しながらツイストを踊っていた集団の呼称。「ロックンロール族」とか「フィフティーズ」とも言った。男性はリーゼント、サングラス、革ジャンなど、女性はポニーテール、Gジャンやスカジャン、パニエで膨らませたスカート、サドルシューズなどのファッション。原宿「ピンクドラゴン」「クリームソーダ」などのショップがローラー族の聖地。
注11 ブティック竹の子 ローラー族と同時期に代々木公園脇の歩行者天国で踊っていた竹の子族のファッションを販売していたショップ。1979年オープンで、今も当時と同じ竹下通りに現存する。創業者の大竹竹則が着心地が良くて動きやすい服として「ハーレムスーツ」を考案、年齢制限でディスコに入れない高校生らが外で踊り始めて次第に「竹の子族」になったという。
注12 くれない族 「夫が家事を手伝ってくれない」のように、「~してくれない」の言葉を多用する人の総称。1984年に放映されたテレビドラマ「くれない族の反乱」から生まれ、ユーキャン新語・流行語大賞の流行語部門の銀賞を受賞した。(実用日本語表現辞典より)
【対談ゲスト】 酒井順子(さかい・じゅんこ)
エッセイスト。1966(昭和41)年東京生まれ。高校時代より雑誌「オリーブ」に寄稿し、大学卒業後、広告会社勤務を経てエッセイ執筆に専念。2003(平成15)年に刊行した『負け犬の遠吠え』はベストセラーとなり、講談社エッセイ賞、婦人公論文芸賞を受賞。著書に『子の無い人生』(KADOKAWA)、『男尊女子』(集英社)、『家族終了』(集英社)、『消費される階級』(集英社)、『老いを読む 老いを書く』(講談社現代新書)など多数。