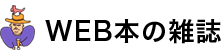作家の読書道 第194回:石井遊佳さん
新潮新人賞を受賞したデビュー作『百年泥』が芥川賞を受賞、一躍時の人となった石井遊佳さん。幼い頃から本を読むのが好きだった彼女が愛読していた本とは? 10代の頃は小説を書けなかった理由とは? インドのチェンナイで日本語教師となる経緯など、これまでの来し方を含めてたっぷり語ってくださいました。
その6「チェンナイでの執筆と読書」 (6/6)
――どうしてもインドに行きたい、と。
石井:私は行く気はないんですけれど彼は虎視眈々と狙っていて、そのために日本語教師になったわけです。彼ももう大学は辞めているし学位論文もたぶんもう出さないだろうけれど、サンスクリット語を極めたいので、そのためにはインドにいたほうが勉強の機会があるんですよね。大学の先生に聞きに行ったり、シンポジウムがあったり、いろいろイベントがあるので、彼はインドに行きたいわけです。そうしたらたまたまチェンナイから求人があって、面接だけ受けに行ったんですね。希望者も多いし駄目だろうと思っていたら、一応学歴はあるしヴァーラーナシーにいたこともあるし、面接に来た会社の人に「妻もネパールで日本語教師をやっていたんですよ」と話したりで、「お二人で来てください」という話になっちゃって。勝手に決められたんです。旦那にいきなり「決まったから一緒に行くからね」しれっと言われて「聞いてない」と思って。
それで、2015年に南インドのチェンナイに行くことになって。私は日本語教師としての教育をまったく受けていないんです。ネパールの時はほとんどボランティアだったので適当にやっていたんだけれど、今度はお金をもらって、日本語学校ではなくIT企業内部の研修の一環としてやることになったんですね。そこの会社は日本にも支社があってこっちに来る人も多いので、必要があって仕事の合間に日本語を勉強させているんです。だからちゃんとやらなくちゃいけないんで、毎日毎日、次の日に何をやるかっていう、教案作りで必死で、土日も休めなくて、だからもう小説どころではなくて。3年くらいそんな思いをしたのかな。チェンナイに行くまでの時期もずっと働いていたので、ちょっと思いついたら1節を書くとか、ある場面だけを書くとかいったメモ書き程度はしていたんですけれど、下手したら4~5年まともに小説を書いてなかったかもしれないです。そんな状態でいた時に、たまたま2~3か月授業が空いたんですね。彼らはプロジェクト単位で動いていて、プロジェクトとプロジェクトの合間に時間があったら日本語を勉強しなさいってことで朝から晩まで日本語漬けになるんですけれど、仕事が混んでいる時はまったくできないので、そういうふうに空いてしまう時期もあるんですね。それまで教室で面白いことがあったらメモしていましたし、洪水のこともあったので、「書けー!」と思って書きました。
――デビュー作にして芥川賞受賞作の『百年泥』は、チェンナイに日本語教師としてきた主人公が洪水で数日間家に閉じ込められ、水が引いた朝に出かける時の光景を描いたものですよね。その洪水も実体験だったという。
石井:そうです。もうそれまで結構長い期間本格的に書いていなかったんですが、奇跡的に書けたんですよ。それで3月末の締切がいくつかあったので、新潮新人賞ともうひとつ出して、そちらは落ちたけれど新潮社からは7月くらいに「最終選考に残った」ってお知らせをいただいて。たまたま日本に1か月くらい帰る予定の時期だったので、編集者にもお会いしてできました。チェンナイへ戻ってからもいろんな文芸誌にエッセイとかも書かせていただいて、そうこうしているうちに芥川賞をいただいて、あれよあれよという間に生活が激変しました。
――まさに急展開ですね。ところでチェンナイに転居する際に、本を厳選して持っていかれたようですね。開高さんの『ロマネ・コンティ・一九三五年』とか...。
石井:開高さんはそれで、あとは三島の『愛の渇き』、中勘助の『銀の匙』、セリーヌの『夜の果てへの旅』、ガルシア=マルケスの『百年の孤独』と『族長の秋』。それくらいかな。
――チェンナイでは日本語の本の入手は難しいですか。
石井:無理ですね。どうしてもといえばamazonで買って親元に送り、それを送ってもらっています。帰ってきた時にいっぱい買って送りもします。ここまで言いませんでしたが、じつは私、エンタメ系もよく読むんですね。選び方はいい加減で、amazonで下のほうに関連本として出てくるものを見てアットランダムに選んでいるだけなんですけれど。わりと読んでいたのは横山秀夫さん。『半落ち』を前に読んで面白かったから。他には、雫井脩介さんとか、奥田英朗さんとか、ずいぶんインドで英気をもらいました。
――じゃあ、インドでの読書生活をいうと、同じ本を繰り返し読んだりとか?
石井:自分の小説を書く時、書きだす前にリズムを整えたいんですね。セリーヌを読んだりガルシア=マルケスを読んだりして、自分の文を書く感じなんですよ。それとは別に息抜きで読む本もあって、それが結構エンタメ系の人なんです。
――『百年泥』はマジックリアリズムを感じさせる内容ですが、やはりマルケスなどの影響があると思いますか。
石井:そうなるんだろうと思いますけれど。本当に自分が好きなくだりを何回も何回も読んだりするので、もう完全に内面化しちゃってて、書いていると出てくるんですよ。マジックリアリズムの手法を用いてここを書きましたという感覚は全然なくて、書いているうちにけったいなことが自然に出てくる感じです。むしろリアリスティックなところのほうがちゃんと考えて書いているところがありますね。
――確かに計算では書けない感じですよね。空を飛んで通勤する、とか。
石井:読んだ人から「インドでは本当に飛翔通勤するんですか」と訊かれるんですけれど、もちろんしません(笑)。当たり前のように書いているから「あれ、もしかしたら」と思うようです。
――さて、お時間も迫りましたので、今後の予定をお聞かせください。
石井:まだ、いつインドに戻るか決めていないんですよ。日本語教師も体力的にきついですし、せっかく芥川賞をいただいたので作家に専念したいと思っておりますので、そろそろ日本語教師からはおいとましようかと。旦那は引き続き同じ会社で教えていますから、その会社の日本の支社で何かできることはあるか訊いてみようかなって。インドには旦那もいるし荷物もいっぱいあるので時々行くけれど、今後はできれば日本中心で活動できればと考えております。
今は、次の小説を血を吐きながら書いているんですよ(笑)。またインドものということで。頑張ります。
(了)