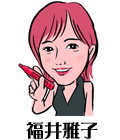WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年11月 >『李世民』 小前亮 (著)
評価:![]()
三国志が大好きなので、漢字ばかりの人名や地名を覚えるのは得意。でも、そうじゃない人は、さぞや苦労するんだろうな〜と思いつつ読みました。本作でも、登場人物が沢山いますが、まず、同じ姓の人が出てきたら「親戚か何かだな」とくくって考えてはどうでしょう?時代は随の終末から唐の初めまでを扱っているので、「遣隋使」「遣唐使」と同じ頃、と覚えてもらうといいでしょう。さて、唐の太宗・李世民を主人公にした話は、初見だったので、「随打倒」という共通の目的で立ち上がった群雄達が、時に結び、時に敵対しながら淘汰されていく様を、面白く読めました。誰がトップに立つかは、最初から決まっているわけではなく、ほんのちょっとした印象や、運だったりする。中でも、バカ弟のとばっちりを受けて次期皇帝の座をフイにする李家の長兄は、不運というしかない。でも逆に、理不尽だからこそ救われた歴史も、同じくらいにあるでしょう。
評価:![]()
本作は唐朝初代皇帝李淵が挙兵してから息子の李世民が皇帝になるまでを、多くの登場人物に満遍なくスポットを当てながら描いた歴史小説で、当時の情勢等がわかりやすく書かれていて非常に読みやすかったのですが、特定の事件や人物をあまり深追いしていないので、小説としては淡白な印象を受けました。当時の情勢などがわかりやすく描かれているので、中国歴史小説の入門書として良いかも知れませんが、逆に詳しい人にはちょっと物足りないかも知れません。
李世民が兄弟を殺す理由は史実だけを読んでいると理解出来ない部分もありましたが、本書を読んで、そういう状況もありえるか、と少し理解出来たような気がします(もちろんその状況はフィクションでしょうが)。中国語で「故事」とは単に昔話を指す言葉ではなく、物語のことなのだそうです。いろいろな思惑を持った人たちの物語が重ね合わさって歴史が作られていくということがよくわかる小説でした。
評価:![]()
中国の歴史小説といえば「三国志」に「水滸伝」が第一に思い浮かぶ。でも、「李世民」というとピンとこないですよね。誰のことかと思ったら、唐朝の第2代皇帝のこと。李世民が、父の李淵、兄の李建成とともに太原で挙兵し、中国全土を平定し唐王朝を築くまでのお話だ。
前半、各地で勃興する勢力の話と、覚えにくい名前にすっかり混乱させられてしまった。ページ数の多さに挫折しそうだったが、すがすがしい魅力あふれる李世民(ちょっとさわやかすぎるような……)の活躍が増えてくると、そんなことも忘れてしまっていた。敵だった勇猛な武将や知将が、やがて彼のもとに集まり、次々と戦に勝っていくところは盛り上がるし見どころだ。だからこそ、前半部分はもう少しすっきりみせてほしかった気もする。デビュー作でここまで読み応えのある作品が書けるだけで、すごい事なのだろうけれど。
李世民以外にも、すばらしい武勇の活躍もあって楽しませてくれる。歴史小説はおもしろくてナンボと思う私には、こういうワクワク感を味あわせてくれる本は大歓迎だった。
評価:![]()
のちに唐朝第二代皇帝となる李世民を主人公に、群雄割拠の中国を描く歴史小説。李世民はもちろんだが、覇権を争う諸国の将軍たちにもそれぞれの物語があって、それがある程度踏み込んだところまで描かれているため、物語に厚みがあり、また多角的に一時代をとらえたスケールの大きな作品に仕上がっている。
しかし、それゆえに本は厚く、登場人物はとても多くなり、著者に負けないほどの興味と熱意がある読者はいいのだが、何の予備知識もなく読み始めた読者は途中で置いていかれそうになるかもしれない。熱意あふれる意欲的な作品であることは間違いなく、読者をその熱さにシビレさせる佳作なのだが、その熱意ゆえかやや欲張りにあれもこれもつめこみすぎたように、ふつうの読者である私には感じられた。
何はともあれ、この作品の李世民はとても男前! 彼の活躍を読むだけでも十分に楽しめる。
評価:![]()
中学校の図書室で、昼休みに男子が夢中になって横山光輝の『三国志』を読んでいた。高校の漢文の授業で生き生きとしだす中国史マニアもクラスに一人はいたような気がする。彼らを見ていると、中国の歴史ものって男子が必ず通る道なのかしら、と思ってしまう。私はというと人物が認識できるか心配で映画『レッド・クリフ』を見に行くかどうかためらっているほどの中国史音痴。
そんなわけなので、登場人物の漢字が読めず名前が覚えられず大変苦戦しながら読んだ。冒頭に登場人物紹介がついているので参照しながら読むのだけれど、簡単な紹介しか書いていないし、物語の中の情勢はめまぐるしく変わっていく。せめて登場人物の振り仮名が、最初だけでなく章が変わるたびについていればいいのに…と感じた。
物語は各地で覇権を争う武将達のそれぞれの活躍が描かれるので、タイトルどおり李世民の一代記を想像して読むと期待はずれかもしれない。
日本の武将達は敵の陣営に寝返るくらいなら自害をするイメージがあったから、敵方の武将が割と簡単に寝返ることになるのが意外。それが小前亮の描く李世民のカリスマ性の表れなのかもしれない。
WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年11月 >『李世民』 小前亮 (著)